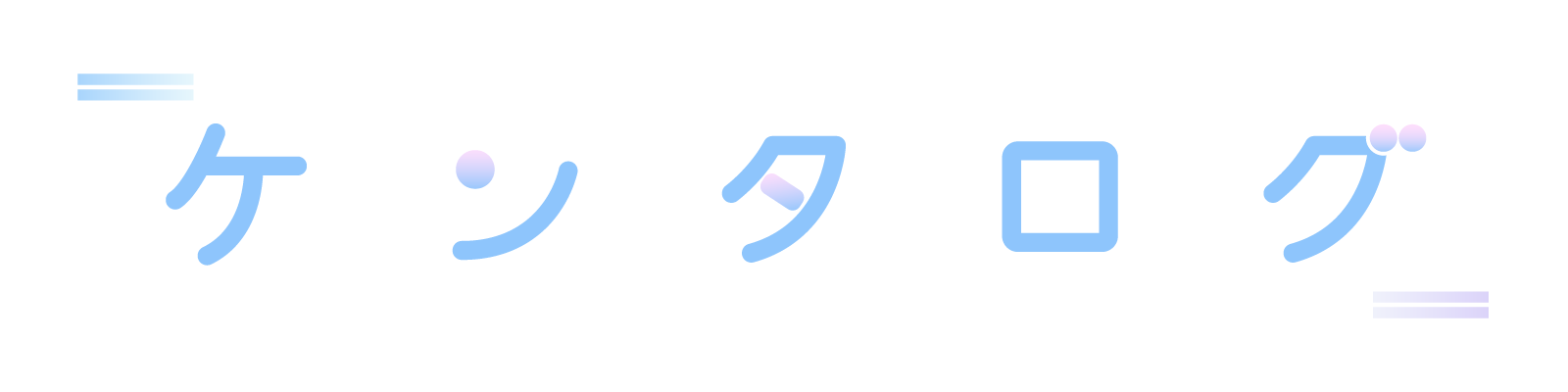研修医必見!症例報告スライドの作り方基本ガイド

症例報告をすることになったけど、初めてで何から始めたらいいのかわからない。。。

初めて症例報告のスライドを作るとき、多くの研修医が同じ悩みを抱えていました。
「どのような構成にすれば良いのか」「文字や色はどう整えるべきか」など、最初の一歩でつまずく人が少なくなかったと思います。(もちろん僕も)
この記事では、症例報告スライドの作り方を構成・文章・デザイン・チェックの4つの視点から丁寧に解説します。
スライドの順番や書き方のコツ、見やすいデザインの基本、発表直前のチェックポイントまでを具体的に紹介しています。

この記事を読み終えたころには、あなた自身のスライドが「聞きやすく、印象に残る発表資料」に変わるはずだす。
研修医としての最初の学会発表を、安心して迎えられるように一緒に準備していきましょう。
- 泌尿器科専攻医として日々の診療と学会発表に従事
- 医局公認デザイン担当として、学会プログラム・抄録集・ポスターを多数制作
- 自身の発表で地方会ベストプレゼンテーション賞を受賞
- 医療系ポスター・スライド制作サービスで累計30万円以上の実績あり
第1章|症例報告とは

研修医として初めて学会や院内カンファレンスで発表する時、多くの人が「どんなスライドを作れば良いのか」と迷うはずです。
症例報告のスライドは、ただ経過を説明する資料ではありません。
診断や治療の過程で得た気づきをチーム全体に共有するための、大切な発表ツールなんです。
短い発表時間で自分の考察を伝えるためには、情報の整理力と構成力が求められます。
スライド作りの基本を押さえることで、内容の伝わり方が大きく変わるはずです。

症例報告スライドを作る目的
「なんで症例報告なんてしないといけないんだろう。」
「スライド作るの面倒くさいな〜」
なんて思ったことあるのではないでしょうか。
スライドを作る目的がわかれば、作成するモチベーションも上がるはずです。

- 経験を整理し、次の診療に生かす
- チームや先輩・後輩に学びを共有する
- 発表を通じて、自分の臨床思考を客観的に振り返る
スライド作成を学ぶメリット
目的を再確認したところで、次はスライド作成を学ぶメリットについて確認しましょう。
短い時間で、自分の考察を伝え、聴衆にとって少しでも学びになってほしいものです。
- 内容の流れが整理され、発表に一貫性が出せるようになる
- 図や表の配置が整い、聴衆に理解してもらいやすくなる
- フィードバックを受けやすくなり、次の症例報告に自信が持てるようになる
症例報告スライドは、「自分の臨床を振り返り、伝える力を鍛えるトレーニング」です。
一つひとつの症例を丁寧に振り返ることで、診療の精度も高まり、チーム医療の質も向上します。
第2章|スライド作成前に準備しておくこと

スライドを作り始める前に、確認しておくべきことがあります。
ここを疎かにしてしまうと、一からやり直しとなりかねない場合があります。
また、事前に準備しておくことで、作業が格段に進めやすくなります。
- 発表の目的を明確にする
- 発表形式・学会や病院の規定を確認する
- 症例データを整理する
- 参考文献を整理する
準備の段階で方向性を決めておくことで、構成の迷いが減り、完成までの時間を短縮できるようになります。
発表の目的を明確にする
何を伝えたいのかを1文で言えるようにしましょう。
「1スライド=1メッセージ」ですが、「1発表=1メッセージ」でもあります。
「これだけでも覚えて帰ってください!」と願いを込めるイメージです。

実際に症例報告をする症例とはどの様なものでしょうか。
以下に4つのポイントを紹介します。
- 普段では経験できないような稀少な症例
- 新たな検査・治療法を導入し、良い結果が得られた症例
- 治療法が進歩しつつあり、治療法自体を複数の医療者で検討したい症例
- 普段から遭遇する症例だが、診療の積み重ねにより特徴的な傾向が見られた症例
あなたが考えていた症例はどれに当てはまりますか?

このように、発表する症例を選んだ意味を確認することで、症例報告の目的が明確になり、結論を導きやすくなりますので、一番最初に考えましょう。
発表形式・学会や病院の規定を確認する
続いて、発表形式の確認です。
発表形式って何?

発表形式・学会や病院の規定とは、ここでは下記に挙げられる様なものを指します。
- 口頭発表(スライド発表) or ポスター発表
- 発表時間+質疑応答時間
- 日程、提出期限
- PowerPointの形式(16:9 or 4:3)、フォント指定、動画使用の可否
- 口頭発表
- 発表5分+質疑応答3分
- 発表日時:2026年4月20日
- 提出期限:2026年4月13日までにデータを送ってください
- スライドサイズ:16:9
- フォント:MSPゴシック
- 動画:使用可
作成途中で指定されていたものと違っていたとわかったら、修正が大変なので、事前に把握しておきましょう。
症例データを整理する
病院から患者情報を抽出するのは、手続きが必要です。
また、抽出するデータを一つ一つ申請するのは面倒くさいです。
施設によって方法は違うと思いますが、僕が普段やっている方法をご紹介します。
パワーポイントに使いそうな画像データや検査結果を貼り付けて、パワーポイントのデータのみを取り出せばいい状態にしておく
このようにすることで、申請するデータは1つだけになります。

参考文献を整理する
参考文献は、文献的考察をするにあたり必要です。
具体的な論文検索方法は下記になります。
- PubMed
- 医学中央雑誌(医中誌Web)
- 科学技術振興機構(J-STAGE)
- Google Scholar
- 学会ホームページなど
実際に導入パートや考察パートで、参考文献の引用元を明示するのですが、作成し始めてから探すのでは遅くなってしまうので、探す環境だけでも整えておきましょう。

また、参考文献はあればあるほど、ごちゃごちゃしてしまいますし、どこに何が書いてあったか忘れてしまいます。
そこで、僕は普段Notionで参考文献を整理しています。

ところどころ抜けていますが、「やっぱり使わないかな」と追加入力しなくなったものです。(リアルな感じが出てますね…😅)

最低限管理しておきたい項目を載せておきます。
- 論文タイトル
- 著者
- 出版年
- PDF or サイトのリンク or doi
- 参考文献記載方法
この章の内容をおさらいしましょう。
事前準備のコツは
- 準備段階で方向性を固めておくと、構成作業がスムーズになる
- データを先に整理しておくと、スライド作成中に迷わなくなる
- 発表形式を事前に把握することで、修正の手間を減らせる
第3章|症例報告スライドの基本構成

症例報告スライドは、構成の組み立てが発表全体の印象を左右します
順序を決めておくと、伝えたい内容が整理され、聴衆の理解も深まります。
順序が定まると、発表全体の流れが自然になり、時間配分の調整もスムーズにできるようになります。
特に初めての発表では、あらかじめテンプレートを用意しておくと安心ですよ。

基本的なスライド構成
多くの学会で共通していた基本構成は以下の通りです。
- タイトル:症例の要点を一言でまとめる
- 背景・目的:この症例を報告する必要性・意義を明確に述べる
- 症例:主訴、現病歴、既往歴、常用薬、家族歴、生活歴など
- 身体所見:バイタル、診察所見
- 検査所見:血液検査、尿検査など
- 画像所見:X線、CT、MRIなど
- 生理所見:心電図、超音波など
- Problem、Assessment
- 治療経過
- 考察:過去の文献を交えて問題解決にどこまで迫ったかを限界を踏まえて考察
- 結論:今回の症例を経験して得られた結論
- 簡単な概要とキーメッセージ
- 参考文献:引用した際にその都度記載するが、最後にまとめておく
時間配分の目安(5分発表の場合)
あくまで参考程度にではありますが、時間配分を紹介します。
- タイトル …… 司会者が言うので割愛
- 背景・目的 …… 30秒
- 症例の概要 …… 1分30秒〜2分
- 考察 …… 2分
- 結論 …… 30秒
- 簡単な概要とキーメッセージ …… 30秒
症例によって、どちらに重きを置くかで異なるため、「症例の概要」と「考察」は逆でもいいと思います。
こう見ると、意外と時間ないなと思うのではないでしょうか。
スライドが多ければ、それだけ話す内容も増えてしまうため、まとめられるところはまとめちゃうのがポイントです。

スライド作成のコツと注意点
これまで発表を繰り返してきた中での肌感で得たコツと注意点を紹介します。
- 各スライドで伝えたい内容を1つに絞る
- 文字を減らして図を増やすと、聴衆の理解が早くなった(気がする)
- スライド枚数は5分発表なら10枚前後が目安
長い文章を読むよりも、図や表でパッと見せられた方が、頭に入ってきやすいです。
スライドを使用した発表(口頭発表)のメリットは、コメントで内容を補えることにあります。
なので、文章やスライド枚数は必要最小限で大丈夫です。

このように、構成を先に固めると、内容が整理されて発表に一貫性が生まれます。
発表時間を意識したスライド構成は、聴衆の集中を保つうえで大きな助けになりますよ。
第4章|文章表現のコツ(スライド文の書き方)

スライドに文章を書くときは、短く・簡潔に・視覚的に伝えることを意識しましょう。
聴衆は発表を聞きながら文字を読むため、長文だと理解が追いつかなくなることが多い印象があります。
スライドならではの書き方の基本をご紹介します。
センター試験模試の国語52点だった僕でも「わかりやすいね」と言ってもらうことができたので、再現性が高いと思っています。

書き方の基本
- 1文はなるべく短く切る
- 1行は15〜20字以内にする
- 1枚のスライドは3〜5行までに抑える
- 「てにをは」を抜かない
- 現病歴は患者が主語、治療経過は医療者が主語
文末の整え方
- 語尾は「〜した」「〜だった」などで統一する
- 「〜にて」「〜を認めた」などの誤った表現は避ける
- 同じ語尾が続かないように変化をつける
- 体言止めは使わない
NG例とOK例を挙げてみます。
実際に口頭で発表するときは丁寧な表現である必要がありますが、記載する文章は丁寧文にする必要はありませんよ。
同じ語尾が続かないようにすることは大切ですが、「ですます調」と「である調」を混合させないように気をつけましょう。
『〜調』は統一する必要があります。

上の文章は体言止めを使用したりと、一見すっきりした文章にはなりますが、統一感には欠けてしまいます。
「認めた」→「確認された」「指摘された」「あった」などの表現に変更しましょう。
一度正しい文章表現で書いた上で、削れるところを探し、調整していきましょう。

注意点とルール
- 略語は初出時に正式名称を併記する
- 単位や数値を統一する
- 個人情報に配慮して匿名化を徹底する
略語は初出時に正式名称を併記する
略語の表現方法をいくつかご紹介します。
具体例として、僕の専門としている泌尿器科で使用する薬物をあげてみます。
フル表記+略語(初出時)
- エンホルツマブペドチン(Enfortumab vedotin:EV)
日本語名+略語
- エンホルツマブペドチン(EV)
英語正式名+略語
- Enfortumab vedotin(EV)
略語 → フル表記
- EV(エンホルツマブペドチン)
略語の意味を説明
- EVは Enfortumab vedotin の略
記事冒頭でまとめて提示
- EV:エンホルツマブペドチン
- ICI:免疫チェックポイント阻害薬
- UC:尿路上皮癌
臨床説明とあわせる
- EV(エンホルツマブペドチン)は既治療UCで使用される薬剤
第5章|デザインとレイアウト(見やすいスライドの作り方)

デザインは発表の印象を大きく左右します。
どれだけ魅力的な内容でも、伝わるデザインでなければ、聴衆には刺さりません。
「どんなにしょうもないことでもデザインがあれば・・・」とまで極端なことは言いませんが、とても大切な要素です。
同じ内容でも、色や文字、配置などを整えるだけで聴衆の理解度は大きく変わります。
配色
- 配色は、4色(ベースカラー・テキストカラー・メインカラー・アクセントカラー)
- 背景は、白または淡いグレー
- 文字色は、真っ黒(#000000)より濃いグレー(#333333や#545454)
- 強調部分だけにアクセントカラーを使用する
より詳細な内容は、「初心者向け|学会発表に最適な配色のコツと方法」という記事で紹介しています。

フォント
- 全スライドで同じフォントを使う
- フォントはゴシック体を使用し、強調部分は太字で表現
- タイトル32〜44pt、本文24〜28ptが読みやすい
- 注釈や表内、参考文献は12〜18ptに抑える(本文の文字サイズとジャンプ率を確保)
おすすめのフォントに関してのより詳細な内容は、「学会発表のポスター・スライドに最適なフォント3選」という記事で紹介しています。

レイアウト
- 要点を3つ以内に絞る
- 行間と余白を広めに取る
- 画像や図表の周囲に余白を確保する
スライドならではのレイアウトに関しては、「初めてでも安心!見やすいスライドレイアウトの秘訣」という記事で解説しています。

図表
- 線を減らしてシンプルにする
- 差を示すときは色ではなく矢印や枠を使う
- 説明文はなるべく短くする
伝わる図表の表現については、今後記事にしていく予定なのでお楽しみに!

第6章|発表前の最終チェックリスト

発表直前には、内容・デザイン・技術の3つを再確認しましょう。
この最終確認を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
内容
- 個人情報を完全に匿名化できている(特にCTやMRI画像は注意!)
- 略語(初回のみfull term)と単位を統一できている(ごちゃごちゃになってない?)
- 引用文献を最新に更新できている(実は新しい文献があるかも?)
- 誤字脱字はないか
- 単位の前には半角スペース
- 正常値と異常値、強調ポイントを強調できているか
- 句読点は統一されているか
- 用語は統一されているか
- 参考文献の書き方は統一されているか
- 英数字の半角と全角は統一されているか
- 菌名はイタリック(斜体)
デザイン
- フォントと色の統一を確認しよう(フォントがズレていると文字間がおかしく見える)
- 文字位置と余白を見直そう(ズレているとそれだけで見栄えが悪くなる)
- 図表のズレを修正しよう(線が引けるか確認)
技術
- ファイル形式を確認し、会場で開けるか試す(当日になることがほとんど)
- USBやクラウドに複数保存しておく(1つ調子悪くてももう1つあれば安心)
- 発表時間を計って練習する(発表時間-30秒の練習をしておこう)
これらを技術というかはなんともいえませんが、本番に備えた実践練習は、本番の余裕を生むために大切な準備です。

第7章|さらにスライドを見やすくするちょっとしたコツ

さらにちょっとした心がけでスライドがガラッと良くなる方法をいくつかご紹介します。
- 文字が多くなる場合は図表で示す
- スライドに載せるのは必要最低限の情報のみにする
- 質疑応答用に情報を取っておく
発表時間には限りがあり、なんでもスライドに載せればいいという訳ではありません。
あえて、発表では触れず、質問してもらう隙を作るのもコツです。
それが結果として、スライドの要素を減らし、すっきりとした発表内容にしてくれますよ。
まとめ
症例報告スライドを作ることは、単なる発表準備ではありません。
自分の診療を整理し、学びを次につなげる大切なプロセスなんです。
- 構成を整えることで、一貫性が生まれる
- 文章を磨くことで、内容が伝わりやすくなる
- デザインを統一することで、理解が深まる
- 最終チェックを行うことで、自信を持って発表できる
丁寧に準備した分だけ、自分の成長が形になります。
症例報告を通じて得た学びが、次の患者の支えになることを願って、素敵な発表にしてください。