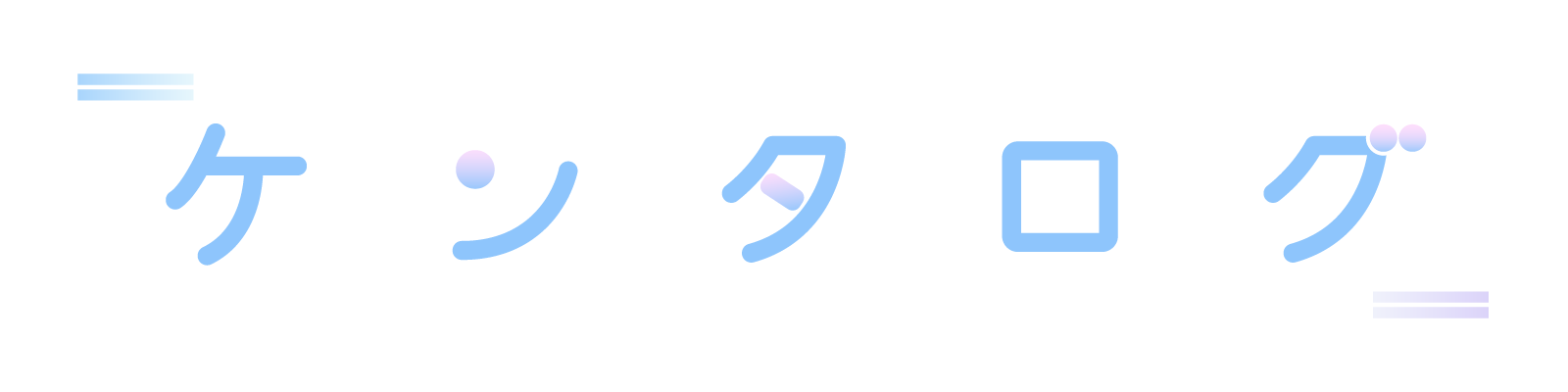ChatGPTで抄読会準備!資料作成を楽にする3ステップ

抄読会が来週になってしまった…💦
まだ論文選びすらもできてない、どうしよう…。

当直や日々の業務で忙しい中、抄読会の準備に何時間もかけるのは正直きついですよね。
「論文を要約する時間がない」
「スライドづくりが間に合わない」
…そんな悩みを抱えている方も多いと思います。
こういった疑問や悩みに答えます。
ChatGPTを活用すれば、文献要約からポイント整理、スライドの骨組み作成まで一気に効率化できます。
この記事を読むことで、限られた時間でも質の高い発表資料を準備でき、余裕を持って抄読会に臨めるようになりますよ。
仕事と勉強を両立したい若手医師のあなたにこそ読んでほしい内容です。
ChatGPTで抄読会資料を作るメリット5つ
ChatGPTを使って抄読会の資料をまとめると、正直かなり助かります。ここでは代表的なメリットを5つ紹介しますね。
① 時間短縮になる
従来だと論文の要約に数時間かかることもありましたよね。
でもChatGPTを使えば、要点をまとめるだけなら10分とかからないんです。
僕も以前は夜中までかかっていた作業が、今では短時間で終わるようになりました。
余った時間をスライド作りや発表練習に回せるのは本当に大きいです。
「忙しい研修医の味方」って感じですね。

② 分かりやすい要約が得られる
ChatGPTは難しい専門用語をかみ砕いてくれるのも魅力です。
例えば、医学論文の難解な英文をシンプルな日本語にまとめてくれるんです。
これなら自分も理解しやすいし、聞き手にも分かりやすい資料になります。
僕も英語論文を要約するときは、必ずこの方法を取り入れています。
「とっつきにくい論文」を「すぐ理解できる内容」に変えてくれるのはありがたいですよ。

③ 見落としを防げる
人間だけで要点を抜き出すと、どうしても抜けや偏りが出てしまいます。
ChatGPTに並行して整理させると「あ、そこも大事だったんだ」と気づけることが多いです。
僕も一人で要約していたときは、意外と重要な点を見落としていたことがありました。
AIをセカンドチェックとして使えば、発表内容のバランスがグッと良くなります。
抜け漏れ防止の保険として、とても頼りになりますよ。

④ スライド作成が楽になる
ChatGPTは「スライドの骨組み」を瞬時に出してくれるのが便利です。
「背景→目的→方法→結果→考察→結論」といった定番の流れもすぐ提案してくれます。
アウトラインが整っていれば、あとは自分で肉付けするだけなので作業が一気にラクになります。
僕はこの方法を使うようになってから、スライド作りのストレスがかなり減りました。
時間も気持ちも節約できるのは大きなメリットです。

⑤ 練習にも活用できる
ChatGPTは発表練習の相手にもなってくれます。
「質疑応答で聞かれそうな質問を挙げてください」と投げれば、Q&A練習ができるんです。
実際にやってみると、本番での想定外の質問にも余裕を持って答えられるようになります。
僕自身もこの練習のおかげで、本番の緊張がかなり和らぎました。
準備から練習まで助けてくれるのは、ChatGPTならではの強みですね。

ChatGPTで抄読会資料を作成する手順3ステップ
ChatGPTを使って抄読会の資料を作る流れを5ステップでまとめました。
研修や勉強会の準備にすぐ使える内容になっていますよ。

① 文献を準備する
まずは抄読会で取り上げる文献を準備しましょう。
文献選ぶと言っても、たくさんある文献をどうやって選べばいいのかわからない…。


文献選びにもChatGPTは、一役買ってくれますよ。
文献を選ぶ手順をお伝えします。一緒に見ていきましょう。
ChatGPTにこのように聞いてみましょう。
PubMedで前立腺癌術後の尿失禁に関する論文を検索したい。最適な検索キーワードを教えて。


こんな感じで出力されました。
今回は、発症時期や回復に注目したいので、こちらを選びます。
(radical prostatectomy) AND
(urinary incontinence) AND
(continence recovery OR pelvic floor muscle training)
先ほど出力された内容をPubMedの検索欄に入力し、「Search」を押します。


抄読会であれば、できる限り新しい内容がいいので、直近5年以内のものに絞るのがおすすめです。
そして、要約と全文が読めるものでなければならないので、絞りましょう。
今回は一番上にあるこちらの記事を読んでいきたいと思います。
Mungovan SF, Carlsson SV, Gass GC, Graham PL, Sandhu JS, Akin O, Scardino PT, Eastham JA, Patel MI. Preoperative exercise interventions to optimize continence outcomes following radical prostatectomy. Nat Rev Urol. 2021 May;18(5):259-281. doi: 10.1038/s41585-021-00445-5. Epub 2021 Apr 8. PMID: 33833445; PMCID: PMC8030653.
ChatGPTにこのように聞いてみましょう。
下記に論文タイトル、要約を載せます。内容を参照して、正確で理解しやすい言葉を使用しながらわかりやすい日本語訳を作成して。
#論文タイトル
Preoperative exercise interventions to optimize continence outcomes following radical prostatectomy
#要約
Urinary ・・・以下続く

するとこんな感じの答えが返ってきました。

わかりやすく、綺麗な文章で要約してくれました。
今回の論文はこれで決定としましょう。
「いまいち日本語訳がピンと来ないな」と思ったら、「中高生にもわかるような平易な表現にしてわかりやすい日本語訳にして」や「〜の部分はどういうニュアンス?」などと追加で質問してみましょう。
また、「他の文献はどうだろう」と思ったら、今の手順を気になる文献を片っ端からやっていきます。
「これにしよう」となるまで時間かかることもあります…。

論文を選ぶことができたら、次は選んで、できればPDFやテキスト形式にしておくとChatGPTに投げやすいです。
要約したいページや図表にマーカーをつけておくと効率がアップします。
医学論文はボリュームが大きいので、一気に全部を処理するより、章ごとに分けて投げた方が正確にまとまります。
まず最初にPDFに出力して、ChatGPTに取り込み、全体像を掴みます。

僕も最初は丸ごと入力して精度が落ちましたが、分割してお願いしたら一気に質が上がりました。
② ChatGPTに要点を整理してもらう
論文を選ぶことができたら、次にChatGPTに文献の要点を整理してもらいましょう。
まずは選んだ論文をPDFで出力します。

画面右の「PDF」をクリックしてPDFで書き出してください。
できたPDFをChatGPTに読んでもらいます。
お願いするプロンプトはこんな感じ↓
こちらは先ほど要約してもらった論文のPDFです。
PDFを読み込み、背景・方法・結果・考察・結論を簡潔にまとめてください。
その結果を元にPICO形式で要点を整理してください。




かなりいい感じに論文の内容が整理されました。
そのまま使うのではなく、自分の理解と照らし合わせながら調整してください。
ここからさらに気になることを質問しながら肉付けしていきます。

AIならではのスピード感を活かして、まずは大枠を掴んでから肉付けしていくのがおすすめです。
③ ChatGPTと一緒に発表の構成を練る
内容が整理でき、気になるところも肉付けすることができたら、発表の構成を練っていきます。
お願いするプロンプトはこんな感じ↓
整理してもらった論文を医局の抄読会でスライド形式で発表したい。「この論文を選んだきっかけ(導入)から論文の紹介、論文の内容の説明、論文を読んで今後の診療に活かす方法」までの構成案を作成してください。





発表の全体像ができました。
これまで、ChatGPTからの提案をスルーしておりましたが、せっかくなので「次にこの構成をベースにスライドごとの見出し+1文要約まで作りますか?」と提案してくれたので、お願いしてみましょう。



いい感じですね。ここでまとめてくれたことが、各スライドごとのポイントです。
スライドの上部や下部に一言添えておくと、聴き手の頭に内容がスッと入ります。
僕が普段伝えている「1スライド=1メッセージ」ですね!

ChatGPTからさらに良さそうな提案があったのでお願いしましょう。






これでほぼほぼ発表内容が完成したと言えます。
細かなニュアンスの違いやより実臨床に落とし込むには人間の力が必須です。
聴き手は人間です。親しみのある発表にすることは僕たちの役目です。
AIの視点に人間の視点を組み合わせて、素敵な発表にしましょう。
本ブログ『ケンタログ』では具体的な発表資料のデザインテクニックなどを紹介しているので参考にしてもらえると嬉しいです。

自分の視点とAIの視点を合わせることで、見落としを防げますし、伝わる発表になると思います。
僕もこのステップを入れてから、発表の説得力がかなり増した気がします。

ChatGPTで使える具体的なプロンプト例
ChatGPTをうまく使うには、「入力する文章=プロンプト」がカギになります。
ここでは、先ほど紹介したプロンプトも含め、実際に抄読会資料づくりで使える便利なプロンプトを紹介しますね。
① 文献要約のプロンプト
下記に論文タイトル、要約を載せます。内容を参照して、正確で理解しやすい言葉を使用しながらわかりやすい日本語訳を作成して。
#論文タイトル
〜
#要約
〜
こちらは先ほど要約してもらった論文のPDFです。
PDFを読み込み、背景・方法・結果・考察・結論を簡潔にまとめてください。
その結果を元にPICO形式で要点を整理してください。
僕は英文論文を読むときに必ずこれを使っています。

② キーポイント抽出のプロンプト
今回はキーポイントの抽出は行いませんでしたが、下記のように聞いてみるのもいいですね。
この研究で重要な点を3つ挙げてください
発表で強調すべき要点を箇条書きで示してください
これを使うと、発表で外せないポイントがパッと分かります。
自分のメモと突き合わせると、抜け漏れチェックにもなります。
このプロンプトで論文理解に対する安心感を得ています。

③ スライド構成のプロンプト
整理してもらった論文を医局の抄読会でスライド形式で発表したい。「この論文を選んだきっかけ(導入)から論文の紹介、論文の内容の説明、論文を読んで今後の診療に活かす方法」までの構成案を作成してください。
ここにさらにこんな条件を加えるのもいいですよ。
#条件
・発表は5分程度
・スライドは10〜15枚程度
・導入に「先日〜なことがあったので」という内容を入れて
・まとめではポイントを3つに絞って紹介したい
などなど、好きなように条件を加えてみてください。
骨組みが一瞬で手に入るので、あとは肉付けするだけです。
スライドづくりの時間を一気に減らせます。
研修の限られた時間には本当にありがたいです。

④ 質問想定のプロンプト
学会発表ほどではないですが、抄読会でも聞かれそうな質問リストを作ってみてもいいかもしれません。
この論文について抄読会で聞かれそうな質問を5つ挙げてください
発表後に想定される疑問点を出してください
これで質疑応答の準備ができます。
僕はこれをやってから本番に臨むと、余裕を持って答えられるようになりました。
ちょっとした安心材料になるのでおすすめです。

ChatGPTを使うときの注意点4つ
ChatGPTはすごく便利ですが、万能ではありません。
抄読会で安心して使うために、知っておきたい注意点を4つまとめました。
① 誤情報が含まれる可能性
ChatGPTはもっともらしい文章を返してくれますが、100%正しいとは限りません。
特に数字や統計データは必ず元の論文と突き合わせて確認してください。
僕も以前、AIの答えを信じ込んで焦ったことがあります。
「便利だけど確認必須」、この意識が大切です。
安全に使うための鉄則ですね。

② 著作権や引用ルールを守る
AIが作った要約も、もとになっているのは文献です。
出典をきちんと明記し、正しい引用ルールを守りましょう。
学術の場では特に重要で、信頼性にも直結します。
抄読会だからこそ「出典意識」を大切にしたいですね。
僕自身も発表では必ず参考文献リストを添えています。

③ プロンプトの工夫が必要
ChatGPTに「要約して」だけだと情報がざっくりしすぎます。
「200字以内」「3つに絞って」など具体的に条件を出すと精度が上がります。
最初は試行錯誤が必要ですが、慣れるとどんどん上手く使えるようになります。
SBSなどで見かける#で条件提示したりするものすごく良いですが、あそこまで詳細にしなくても壁打ちしながら少しずつ理想の形に寄せていくのも良いですよ。
僕も毎回ちょっとずつ工夫しながらプロンプトを改善しています。プロンプト力は経験値で伸びますよ。

④ 過信せず最終確認をする
ChatGPTのアウトプットはあくまで下書きです。
最後は必ず自分の言葉で整理して仕上げましょう。
発表するのは自分自身なので、読み上げながら調整すると安心です。
僕も必ず声に出して確認するようにしています。
このひと手間で、発表の完成度がグッと上がりますよ。

ChatGPTで抄読会をもっと効率化するコツ
ChatGPTをただ要約に使うだけじゃもったいないです。
ちょっとした工夫で、抄読会全体をもっと効率的でレベルの高いものにできますよ。
ここでは実践的なコツを4つ紹介します。
① 質疑応答の想定を準備する
発表の最後に必ずある質疑応答。これもChatGPTに準備を手伝ってもらいましょう。
『質問想定のプロンプト』で紹介したプロンプトを活用することで、想定Q&Aが出てきます。
実際に練習しておくと、本番での安心感が全然違います。
僕もこの準備をしてから、質疑応答が怖くなくなりました。
自信を持って答えられるのは大きな武器ですね。

④ フィードバックを活かす
抄読会が終わったあともChatGPTは役立ちます。
もらったフィードバックをChatGPTに入力して「改善案を出して」と依頼すると、次の発表がもっと良くなります。
僕も「〜ってどうなの?」と言われた後にうまく答えられず、「調べてみます」で終わってしまった内容をChatGPTに伝えて、次の発表の際の着眼点として活かすように心がけています。
終わった後も成長につなげられるのがAI活用の強みです。
次の抄読会に活かせば、どんどん発表が上手くなりますよ。

まとめ
今回はChatGPTを使った抄読会資料の作成手順を紹介しました。
文献の整理からスライド作成、質疑応答の準備まで、AIを取り入れることで作業効率は大きく変わります。
ただし、誤情報や引用ルールには注意が必要で、最終的な確認は必ず自分で行うことが大切です。
ChatGPTをうまく活用すれば、限られた時間でも質の高い資料を用意でき、抄読会を自信を持って乗り切れるようになります。
忙しい中でも効率よく学びを深めたい若手医師の方は、ぜひ今回の内容を実践してみてくださいね。