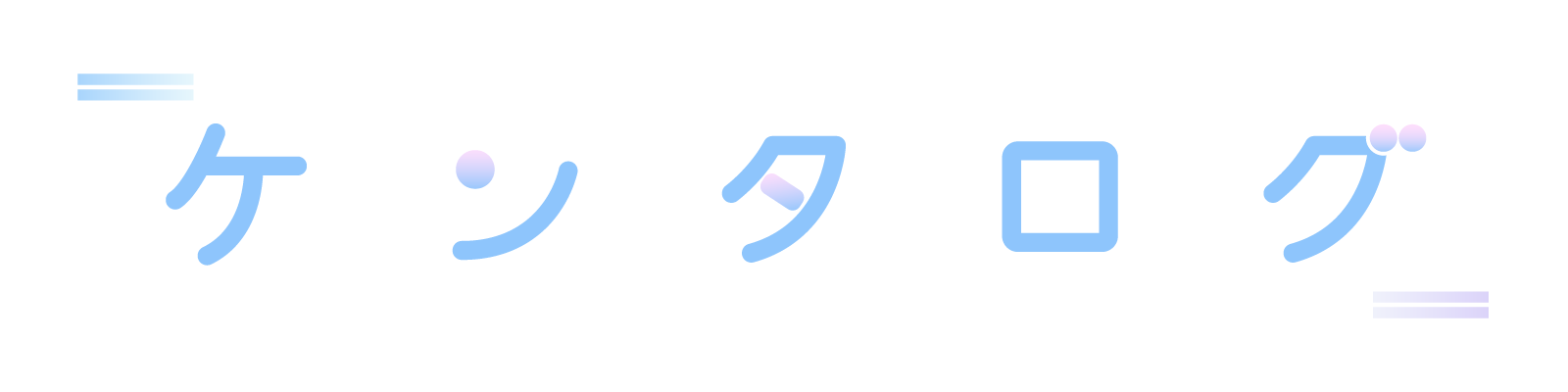研修医必見!初めての抄読会を成功させる攻略ガイド


抄読会ってどうやって準備すればいいんだろう…。
研修医として初めて参加するけど、何から始めればいいの…?
そんな不安を感じていませんか?
初めての抄読会は、論文選びや発表準備、質疑応答への対応など、分からないことだらけで戸惑うものです。
この記事は、初めて抄読会に挑戦する研修医のあなたに向けて、準備から発表までの具体的な方法を解説します。
この記事を読むことで、論文の選び方や読み方、スライド作成のコツ、プレゼン練習のポイントがすべてわかります。
また、聴衆に「分かりやすい!」と思ってもらえるプレゼンの秘訣も学べます。
- 初めて抄読会に挑む研修医
- 論文の選び方や読み方に自信がない医学生
- プレゼンテーションに苦手意識を持つ医療従事者
この記事を読めば、抄読会に必要な基本が身につき、自信を持って発表に臨めるはずです!
抄読会って何をするの?
抄読会は、最新の医学研究を読み解き、実際の診療に活かすための学びの場です。
医学論文を通じて新しい治療法や研究成果について学び合います。
医療の世界は日々進歩しているため、常に新しい知識を学び、それを実践に活かすことが大切です。
抄読会は、そのための重要な機会となります。

抄読会では、論文を深く理解するだけでなく、その内容を分かりやすく説明する力も身につきます。
また、研究の方法や限界について考えることで、医学的な考え方や論理的な分析力も養えます。
特に研修医にとって抄読会は貴重な学びの場です。医学の知識を深められるだけでなく、研究結果を批判的に見る目も養えます。
さらに、参加者との議論を通じて、実際の診療でより良い判断ができるようになります。
「抄読」という語彙は広辞苑には載っていないとのこと。
勝手に色々定義している風ですみません😅

抄読会の目的と大切さ
抄読会がどうして大事なのかを知ろう!

抄読会の目的は、論文を通じて最新の医学知識を共有し、それを実際の診療に役立てることです。
抄読会は、知識だけでなく、論文を批判的に読む力や他者に伝える能力も鍛えられます。
例えば、新しい治療法の効果やガイドラインの変更点を理解することで、患者さんへの診療に役立てることが可能です。
また、議論を通して意見を交換することは、自己成長にもつながります。
意見交換する中で自分の診療方針に磨きをかけるイメージです!

抄読会で学べること
どんなスキルや知識が身につくの?

抄読会では、多くのスキルが身につきます。
- 論文の要点を短時間で把握する力
- エビデンスを批判的に評価する力
- 自分の意見を整理し、わかりやすく伝える力
- 複雑なデータをわかりやすく解説する力
例えば、論文の要点を短時間で把握する力や、エビデンスを批判的に評価する力などです。
また、自分の意見を整理し、分かりやすく伝える力も向上します。
例えば、複雑なデータをわかりやすく解説する力は、プレゼンテーションや患者説明にも役立ちます。
自分で言うのも変な話ですが、普段の外来で患者説明をスムーズになったなと実感してます。

抄読会は、単に論文を読むだけでなく、実践的なスキルを得られる貴重な機会です。
抄読会の基本をおさえよう
抄読会をスムーズに進めるためには、基本的な流れや準備を理解することが大切です。
順序をしっかりと押さえ、テーマの選び方や論文の探し方を工夫することで、効果的に学べます。
初心者は特に、実践的なアプローチを学びながら進めると安心です!

抄読会の流れを知る
抄読会の基本的な流れは以下の通りです。
まず司会者がテーマを紹介し、発表者が論文の背景や結果を要約します。(医局ごとに多少異なります)
その後、参加者全員で議論し、内容を深く掘り下げるのが一般的です。
僕の所属する医局の抄読会の流れをご紹介します!

- 司会者が発表者とテーマを紹介
- 発表者による論文プレゼンテーション
- スライドを使用して論文の要点を説明
- 研究背景、方法、結果、考察の順で解説
- 質疑応答とディスカッション
- 参加者からの質問に回答
- 臨床応用についての議論
- 指導医からのフィードバック
例えば、治療法の効果について具体的なケースを議論すると、実践にもつながります。
このような流れを事前に把握しておくと、当日のイメージが湧き、準備や参加がスムーズになりますよ。
テーマの選び方
初心者には、基本的な臨床スキルや一般的な疾患に関連する論文が適しています。
例えば、診断や治療の新しい方法に関するレビュー論文や、日常診療で頻繁に遭遇する疾患に関する論文が良いですね。
研修医にとっては、自分の臨床経験に基づいたテーマを選ぶことが学びを深める上で重要です。
具体的には、例えば高血圧や糖尿病などの一般的な疾患に関する論文、または新しい診断技術や治療法のレビュー論文が適しています。
参考程度ではありますが、実際に僕がこれまでの抄読会で選んできたテーマをご紹介します。
| 発表する診療科 | おすすめテーマ | 参考例 |
|---|---|---|
| 入局を希望している診療科 | 日常診療で頻繁に遭遇する疾患に関するテーマ 専攻医1年目たちが直面している学びを先取り | 前立腺肥大症の診療ガイドライン、最新治療と今後 |
| 入局を希望していない診療科 | 進もうと思っている診療科に繋がりそうなテーマ | 麻酔科ローテーション中なら:ロボット支援下前立腺全摘除術の術中麻酔管理 |
| 専攻医 | 日々の診療で気になったテーマ | 根治的前立腺全摘除術前後の骨盤底筋体操の効果とタイミング |
論文を選ぶ際には自分のレベルに合わせることが重要です。
最初は身近な内容から始め、徐々に専門性を高めていくのがおすすめです。
医局の先生たちも研修医の抄読会に専門的すぎる内容は望んでいません。
正直な話、「ローテーション中、こんなことを学んで、こんな疑問を感じたから調べて発表してくれたんだな」と思って聴いているはずです。
良い意味で「研修医らしい」テーマを選びましょう。

テーマ選びでは、指導医からアドバイスを受けることで、自分のスキルアップにつながるトピックを見つけることができます。
「気になって調べてみたけど、イマイチしっくりこないところもあるので教えてください!」というのもアリです!

何より重要なのは、その論文が自分の興味を引くものかどうかです。
興味が持てない論文は、時間も労力もかかるだけです。
個人的には論文選びに一番時間をかけても良いと思っています。

興味のある論文を選べば、発表準備の過程がより充実したものになります。
論文の探し方
どこでどうやって論文を見つけるの?


論文を探すには、PubMedやUpToDate、医中誌Web、Google Scholarなどのデータベースを活用します。
検索キーワードを絞ることで、効率よく目的の論文にたどり着けます。
例えば「urology AND guideline」で検索すると、泌尿器科の最新ガイドラインが見つかります。
初心者は、著名なジャーナルから探すと良質な論文を選べるでしょう。
いくつかの代表的なジャーナルを挙げると、以下のようなものがあります。
- The New England Journal of Medicine (NEJM)
- 医学分野で最も権威のあるジャーナルの一つであり、新しい治療法や臨床研究が多く掲載されています。
- The Lancet
- 医学だけでなく、公衆衛生や環境医学にも力を入れているジャーナルです。
- Journal of the American Medical Association (JAMA)
- 幅広い医学分野をカバーし、臨床研究やレビューが豊富に掲載されています。
- British Medical Journal (BMJ)
- 臨床医学から公衆衛生まで、多岐にわたる医学情報を提供する信頼性の高いジャーナルです。
- Nature Reviews Drug Discovery
- 新薬の発見や開発に焦点を当てたレビュー記事を掲載し、製薬業界や研究者にとって重要な情報源となっています。
研修医なら誰もが知ってるはずなレジデントノートにも医学論文の探し方がわかるシリーズがありますので、そちらもおすすめです!

読むべき論文を選ぶコツ
見つけ方はわかったけど、実際どんな論文を選べばいいの?


良い論文の見つけ方を教えます!
読むべき論文を選ぶ際には、信頼性や実用性を重視することがポイントです。
例えば、インパクトファクターが高いジャーナルや、引用数が多い論文は信頼性が高いです。
また、abstractを読み、研究の目的や結果が明確であるかを確認すると良いでしょう。
特に、臨床現場で役立つ内容を選ぶことが、抄読会を有意義なものにする秘訣です。
「インパクトファクター」なんて難しいことを考えずに、明日の臨床に活かせる内容を選びましょう!

論文を読んで準備しよう
論文を読み理解することは、抄読会の成功に欠かせません。
内容をきちんと理解し、必要な情報を整理することで、発表や議論をスムーズに進めることができます。
正しい読み方や準備手順を押さえることで、初めての抄読会でも安心して取り組めます。
論文の読み方
僕が普段やっているおすすめの論文の読み方を紹介します!

論文を読む際は、まずabstract(要旨)を確認し、研究の全体像を把握することから始めましょう。
abstractは論文全体の縮図のようなものです。
目的、方法、結果、結論の概要を掴むことで、次に読むべき部分の優先順位を決められます。
概要を理解したら、introductionやdiscussionに進み、研究の背景や意義を深掘りしていきましょう!

また、図や表は文章とは異なる位置に配置されていることが多いので、対応する箇所を確認しながら読むことが重要です。
英語で読む場合、GoodNotesに取り込み、マーカーを引きながら進めると効率的です。
一方、英語が苦手な場合は、DeepLで翻訳し、翻訳文をNotionにコピー&ペーストして読むと良いでしょう。
僕は後者ですね😅
Notionでもハイライトなどできるのでおすすめです!

ハイライトすべきポイントは後述します。
論文へのハイライトの付け方
論文の内容すべてをスライドに盛り込むのは避けましょう。
それでは、論文をそのまま印刷して配布するのと同じで、発表の意義が薄れてしまいます。
スライドには、聴衆に伝えるべき要点だけを選んで載せたいです。
膨大な文章から重要なポイントはどう選んだらいいの?


作者が伝えたい重要なポイントはAbstractに書いてあります。
ただ、Abstractだけでは簡潔すぎるので、本文を読み込み、自分が伝えたいポイントと聴衆にとって必要な情報を絞り込んで膨らませていきましょう!
- abstractの全体像を理解
- Abstractで示される目的、方法、結果、結論を確認し、大まかなストーリーを掴む
- 例:「研究の目的は新しい治療法の効果を検証すること」
- この段階では、何が重要かを頭に入れるだけでOK
- キーワードを抜き出す
- Abstractの中から、研究の核となるキーワード(例:治療法の名前、主要な結果など)をピックアップ
- これが本文を読む際の指針になる
- Abstructを背景、対象・方法、結果、考察、結論に分類する
- Abstructに記載されている文章を本文内でハイライトする
- Introductionで背景を確認
- Abstractで触れられていない背景や目的の詳細を掴む
- ハイライトするポイント:
- 研究の背景や課題
- 目的や意義が具体的に説明されている箇所
- Methodsで重要な手法を理解
- 発表で必要なら、研究手法や条件を簡潔に説明
- ハイライトするポイント:
- 研究デザイン(例:ランダム化比較試験)
- 方法論で他と違う点や特徴的な部分
- Resultsで主要な結果を明確に
- 結果はスライドに最も反映されやすい部分
- ハイライトするポイント:
- データの概要(例:治療Aが30%改善)
- 図表やグラフで補足されている箇所
- Discussionで結果の意義を補足
- 結果が何を示しているのか、著者の解釈や今後の課題を確認
- ハイライトするポイント:
- 結果の解釈とその理由
- 臨床応用や今後の研究への示唆
こんな感じでやっていくと全体像を掴みつつ、スライドにしたい部分も明確にしながら読めるのでおすすめです。
この作業がしやすいという点で、GoodNotesやNotionはおすすめのツールです。
今後、実際にハイライトをつけていく様子も記事にしますね!

発表スライドを作ろう
発表スライドは、内容をわかりやすく伝えるための重要なツールです。
シンプルで明確なデザインを意識し、情報を整理することが成功のカギとなります。
スライド作成のコツや手順、効果的なデザインのポイントを解説します。
スライド作成のコツ
スライドは1枚につき1つのメッセージに絞ると効果的です。
文字数を抑え、図やグラフを活用することで視覚的に伝わりやすくなります。
例えば、治療の比較を表にまとめると、聴衆の理解が深まります。
また、フォントや色使いを統一し、視覚的な一貫性を保つことも重要です。
過剰な装飾を避け、内容が際立つデザインを心がけましょう!

- アウトラインを作成
- スライドに落とし込む
- デザインを調整する
スライドに落とし込むのは本当に最後なんだ。
この記事読む前、真っ先にパワポ開いてたよ。


そうですね。パワポを開くのはスライドに落とし込む準備が整ってからです。
アウトラインを作成しよう
スライド作成の第一歩は、発表の全体像を明確にするアウトラインを作ることです。
- 伝えたいメッセージを整理
- 聴衆に伝えるべき主要なポイントを箇条書きでリストアップします。
- 発表の流れを構築
- ストーリーを意識し、アウトラインを作成します。(後述)
- 1スライド1メッセージを意識
- 聴衆に負担をかけないために、1スライドに詰め込む内容を最小限にします。
各スライドの主な役割を解説しますので、先ほどハイライトしたものを当てはめていきましょう。
| 構成 | 主な内容 |
|---|---|
| イントロダクション | 発表の目的と概要 |
| タイトル | 簡潔でわかりやすいタイトル |
| 導入 | 日常生活で気になったこと・気づいたことをきっかけに今回の論文を選択したことを伝える |
| 今回の文献 | 読んだ論文を紹介 |
| 背景 | 研究のテーマや目的を簡潔に説明し、その重要性を伝える なぜこの研究が必要だったかを示すことが大切 |
| 対象・方法 | どのような対象者を選び、どのようにデータを集めたかを簡潔に説明 |
| 結果 | 主要なデータや成果をグラフや表で視覚的に示し、要点を強調する |
| 考察 | 結果から導かれる知見や限界点について説明し、どのように解釈するか提案する |
| 結論 | 論文で述べられている最も重要な発見と、それが医療現場どのように役立つのかを明確に述べる |
| まとめ・Take home message | 自分が思う今回の文献の要点 今回の論文を読んで今後に活かせること・伝えたいこと |
当てはめられましたか?
それでは次のステップに移りましょう!

スライドに落とし込もう
アウトラインを基にスライドの骨組みを作ります。
- タイトルとサブタイトルを設定
- スライドごとに適切なタイトルを付け、内容が一目でわかるようにします。
- 例:「研究の目的」「主要な結果」など。
- テキストを簡潔にまとめる
- 長い文章を短いフレーズや箇条書きに変換します。
- 悪い例:「この研究では新しい治療法の有効性を検証しました。」
- 良い例:「新治療法の有効性を検証」
- 図表やグラフを配置
- 結果を視覚的に伝えるため、本文や論文から必要な図表をスライドに挿入します。
- 例:治療の比較結果や統計データを示すグラフ。

デザインを調整する
内容をスライドに反映させた後は、デザインを整えて見やすく仕上げます。
- レイアウトを統一する
- 全スライドでフォント、色、余白の使い方を統一します。
- これにより、視覚的な一貫性が生まれます。
- 例:見出しは大きめの文字、本文は中サイズのフォントを使用。
- 余白を意識する
- 詰め込みすぎを避け、スライドの余白を活用して情報を見やすくします。
- 強調したい箇所を目立たせる
- 色や太字を使い、重要なデータや結論を強調します。
- 例:「30%改善」という結果を赤字や背景・枠で目立たせる。
- 視覚的要素を活用する
- アイコンやイラストを加えて、聴衆の注意を引きやすいスライドを作ります。



発表をもっとよくする工夫
発表をさらに良いものにするためには、わかりやすい話し方や練習、質疑応答への備えが重要です。
それぞれのポイントを押さえておけば、聴衆にとって魅力的で有意義なプレゼンテーションになりますよ。
聴く人に「なるほど」「面白い」と思ってもらえる発表にしたい!


せっかくの抄読会ですから、楽しく学びのある会にしたいですよね!
わかりやすいプレゼンのコツ
プレゼンでは、内容をストーリー仕立てにすることで聴衆の関心を引きやすくなります。
アウトラインの場所でも触れていますが、今回の論文を選んだきっかけは聴衆に興味を持ってもらうために大事なステップです。
また、専門用語を減らし、簡潔な言葉で話すことも重要です。
専門家の前で話すとは言っても専門用語ばかりでは疲れてしまいます。

「患者さんに聞いたらこんなこと言ってました」といった具体例やエピソードなどもあると説得力が増しますね。
もちろんデザインも超重要で、視覚的にもわかりやすいスライドを活用し、内容の理解を促しましょう。
プレゼン練習の大切さとやり方
緊張せずに話せるようになりたい!


発表を成功させる鍵とにかく反復練習することです!
まずは時間を計りながら通して話す練習を行い、内容の流れを確認しましょう。
その後、友人や同僚に聴いてもらい、フィードバックをもらうことが効果的です。
録音や録画を利用すると、自分の話し方や声のトーンを客観的に改善できます。
僕だけかもしれませんが、自分の声を客観的に聞くとなんか気持ち悪いんですよね…。

そんなわがままは言ってられません。本番を想定した練習を繰り返して、自信を持って発表しましょう。
質疑応答での対応方法
質問されたときに動揺を見せずにスマートに答えたい!


ここできちんと答えられるかが、「内容を理解しているな」って思ってもらえる大事なポイントです!
質疑応答では、まず質問をしっかり聞き取り、要点を繰り返すと誤解が防げます。
答えがすぐに思いつかない場合は、「詳しく調べて後ほどお答えします」「宿題にさせてください」などと素直に伝えましょう。
これは学会発表でもとても大事なことです。
わからないことを誤魔化さないことです!

まとめ|抄読会で成功するための基本と準備方法
抄読会を前に、「どう準備すればよいのか分からない」「発表や質疑応答が不安」といった悩みを抱えている方も多いでしょう。
本記事では、抄読会初心者でも安心して取り組めるよう、準備から発表までの具体的な手順を解説しました。
ここでは、特に重要なポイントをおさらいし、次の行動につなげていきましょう。
- 抄読会の意義
- 医学知識を学び、実践や研究に活かす場
- 批判的思考や伝達スキルを養うための学びの機会
- 他者との議論を通じて理解を深める
- 準備と進行の基本
- 適切なテーマと論文を選び、必要な情報を整理する
- 流れを明確にし、要点をスライドに簡潔にまとめる
- 論文の読み方
- 論文全体を見渡し、重要な部分を段階的に深掘りする
- 図表と本文を照らし合わせて全体像を整理する
- スライド作成と発表のコツ
- 情報を簡潔に伝え、視覚的にわかりやすくする
- 論文の全てを盛り込まず、聴衆に必要な要点を絞る
- 練習と応答の工夫
- 繰り返し練習して流れを確認し、自信をつける
- 質疑応答は正確さと誠実さを心がける
本記事を通じて、抄読会の準備と発表の基本を理解いただけたでしょうか。
特に初心者が躓きがちなテーマ選びやスライド作成について、具体的なアドバイスを共有しました。
これらを実践することで、抄読会への不安を軽減し、自信を持って取り組めるはずです。
次のステップとして、実際に論文を選んで読んでみましょう。
その後、今回紹介したスライド作成の手順を活用し、1つの完成したスライドを作ってみてください。
繰り返し準備を進めることで、より高いプレゼン能力を身につけることができます。
あなたの成功を心より応援しています!