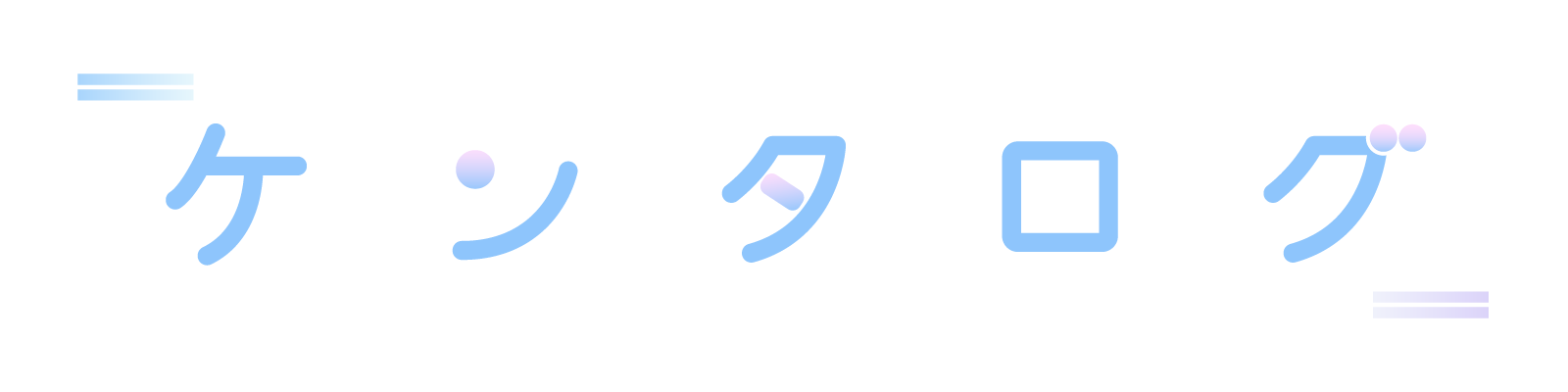医療者に必要な「デザイン思考」とは

センスがないからスライド作りは苦手…。
デザインなんて、本質的な医療行為じゃないよね… 。

そう感じている医療者は、少なくないと思います。
しかし、それはデザインに対する誤解です。
医療におけるデザインとは、見た目をきれいに飾ること(デコレーション)ではないんです。
複雑な医療情報を整理し、誤解なく、正確に伝えるための設計(デザイン)です。
不適切な薬剤指示が医療事故を招くように、わかりにくいスライドやポスターは医学の理解や進歩を静かに妨げてしまいます。
本記事では、
なぜ今、医療者に「デザイン思考」が不可欠なのか
その本質を同じ医療者の視点から整理したいと思います。
- 泌尿器科3年目(医師5年目)
- 地方会ベストプレゼンテーション賞を受賞
- 医局の公認デザイン担当として、学会関連資料の作成
- ココナラでの資料作成サービスで総売上30万円以上
具体的なテクニックについては、この記事の考え方を前提として、別の記事で詳しく解説しています。

デザインは「装飾」ではなく「機能」
多くの人が「デザイン」と聞くと、芸術的センスや美しい装飾を思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし、語源であるラテン語 Designare は、「計画を記号に表す」という意味を持ちます。
つまり、デザインとは、「課題を解決するための設計図」なんです。
- 課題:聴衆が眠くなる、データが伝わらない
- 解決:視線の流れを設計し、ノイズを削ぎ落とす
スティーブ・ジョブズはこう言いました。
Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.
デザインとは、単にどう見えるかではない。どう機能するかだ。
医療に置き換えると、とても自然な考え方になります。
診療も手術も、「きれいに見えるか」ではなく、「安全に、確実に、再現性をもって機能するか」が最優先されます。
その延長が、結果として美しい術野になるんです。(指導医の術野は無駄がなく、美しいと日々実感しています。)

デザインも同じで、目的は”映えること”ではなく、「正しく伝わり、誤解が起きないこと」です。
「センス」は不要、必要なのは「ルール」
デザインという言葉を聞くと、「センスがある人じゃないと無理」と感じてしまう方も多いでしょう。
しかし、医療は本来「ルールの世界」です。
治療プロトコルや診療アルゴリズムがあるように、デザインにも再現性のある法則があります。
デザイン思考を叶える思考手順
医療者向けに整理すると、デザイン思考は次のような「思考の手順」で成り立っています。
- 何を一番伝えたいのかを決める
- 情報を重要度で整理する
- 読む順番(視線の流れ)を整理する
- 不要な情報を削る
- 誤解が生まれない形に整える
これらはすべて、才能や感覚ではなく、「考え方の型」です。
だからこそ、医療はデザインと相性がいいと思っています。
「センスがないからできない」のではなく、ルールを知らなかっただけなんです。
「認知負荷」を減らし、医療安全を高める
医療現場は、常に情報過多です。
電子カルテ、検査データ、論文、ガイドライン。
僕たちは膨大な情報の中から、短時間で正しい判断を求められます。
ここで重要になるのが、「認知負荷(Cognitive Load)」の軽減です。
- 文字が詰め込まれたスライド
- 色のルールが統一されていないグラフ
- 整列されていないレイアウト
これらは、読み手の脳に不要な負担を与え、理解の遅れや解釈ミスを引き起こします。
認知負荷が高い状態では、
- 重要な情報が読み飛ばされる
- 優先順位が正しく伝わらない
- 判断に余計な時間がかかる
といったことが起こってしまいます。
臨床現場で言えば、「情報が多すぎて全体像が掴めない状態」と同じです。
つまり、“伝わらない”のは、説明不足ではなく、情報設計そのものの失敗なんです。
文字が多すぎて、何を理由に入院していて、治療の進捗状況がわからない入院カルテを見かけることがあるのではないでしょうか。

資料作成に話を戻すと、情報設計をして、デザインの基本原則(近接・整列・反復・対比)を用いて再現することで、認知負荷を軽減することができるようになります。
デザインにより情報のノイズを除去し、情報を正確に伝えることで、結果として医療安全を高めるためのリスクマネジメントにもなるんです。
デザインの基本原則については、こちらの記事で解説しています。

相手の時間を奪わない「敬意」の表明
学会発表や抄読会において、聴衆の時間は「共有財産」です。
読みにくいスライドで発表することは、その場にいる全員の時間を奪っているのと同じです。
- 一目で結論がわかるスライド
- 3秒で理解できるグラフ
これらを用意することは、忙しい同僚や先輩、そして患者さんへの「敬意(Respect)」の表明でもあるんです。
発表者側にも「情報の受け手」が理解に集中できる環境を作る責任があるんです。
まとめ
医療者に必要な「デザイン思考」は、アーティストのような感性ではありません。
「誰に、何を、どう伝えるか」を論理的に組み立てる技術です。
- 情報を整理する
- 不要なものを削る
- 視線の流れを設計する
これらは、外科医が結紮を練習するように、内科医が臨床推論を磨くように、トレーニングで身に付く臨床スキルの一つです。
明日からの資料作成では、まず「装飾」をやめ、「整理」することから始めてみてください。
それが、「医療×デザイン」の第一歩です。